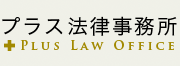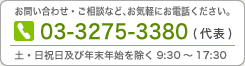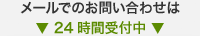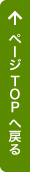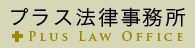◆ 建築トラブルに関する全国Web相談のご案内
事件受任だけでなく継続相談によるサポートも実施しています。
お問合せフォームよりお申込ができます。お気軽にご相談ください。
経歴
得意分野
■ 建築紛争、欠陥住宅・リフォーム
必要に応じて、建築士や地盤品質判定士などの専門家と協力して問題の解決に当たります。地盤の問題は、さらに専門性が極めて高い分野ですので、地盤品質判定士などの専門家と協力して問題の解決に当たります。
■ 不動産取引の問題
裁判例を分析して、専門的知見をもとに、リスクの説明や問題の解決に当たります。
■ 建築の問題に関する第三者委員会
不祥事を起こした建築会社としては、消費者の立場に立った専門家を委員に選任し、消費者に代わって徹底調査を行わせる姿勢が重要になります。
■ マンション管理に関する意見書作成
企業の第三者委員会として活動した知見を生かして、マンション管理や管理組合の問題に関する外部調査、意見書作成を行った実績があります。
トピックス
2015年3月30日
株式会社県民共済住宅の壁量不足問題につき第三者委員会の委員就任 調査報告書の提出
2015年10月20日
NHKクローズアップ現代「『傾いた』マンション 相次ぐ欠陥工事はなぜ」出演
2015年10月27日
NHKラジオ先読み!「マンション傾斜問題波紋広がる 暮らしと安全を守るには」出演
2015年11月18日
NHKあさイチ「あなたの家は大丈夫?!欠陥住宅トラブル」出演
2017年6月14日
NHKニュース シブ5時 サブリース契約に関するインタビュー出演
2017年6月27日
地盤工学会・地盤品質判定士協議会共催の「宅地地盤の評価に関する最近の知見講習会」内
「地盤に関わる訴訟事例から見た地盤分野特有の課題」講演
2017年9月22日
日経ホームビルダー第220号48頁「“契約の虎の巻”が標的に 消費者団体が是正申入れ」
インタビュー記事が掲載
2018年3月6日
第二東京弁護士会主催の会員向け研修会「大規模地震等被災時の住宅紛争に関する判例解説」内
「地震による地盤の液状化」講演
2019年1月15日
一戸建て購入検討者を応援する口コミ掲示板サイト「e戸建て」内
特別企画住宅コラム「欠陥住宅裁判で負けないための被害者の心得」掲載開始
2019年3月7日
第二東京弁護士会主催の会員向け研修会「使おう、住宅紛争審査会!」内
「紛争解決事例(モデルケース)」解説
2022年1月29日
地盤品質判定士会主催の「地盤品質セミナー」内
「地盤に起因する建築紛争について-地盤品質判定士への期待-」講演
建築紛争の事例解説
■汚水逆流事故で慰謝料請求した事件
事件受任に至るまで
本件は、歯科医師である施主が、歯科クリニックを開業するにあたり、鉄筋コンクリート造建物の1階店舗区画をスケルトン状況から歯科医院の内装にする工事を施工業者に発注したところ、配管工事の欠陥により、トイレや流し台などから汚水が逆流したというショッキングな事案です。
一般的に、歯科医院の配管は、患者が座って治療を受ける歯科ユニット、口腔内バキューム、口腔外バキューム、消毒コーナーの洗面台、職員用のトイレの手洗い場、患者用のトイレの手洗い場などの雑排水管があり、これとは別に、職員用のトイレや患者用のトイレの下水管があり、さらに、それぞれの給水管があるので、床下には多数の給排水管が敷かれており、この空間を確保するため、約30㎝の床上げ工事が行われています。
本件工事の排水計画は、当初の設計では、雑排水と下水を明確に分けて、相当な口径の配管が設置される計画でした。ところが、施工業者は、施主の了解を得ることなく、トイレの下水管に、一部の歯科ユニット、消毒コーナーの洗面台、トイレの手洗い場などの雑排水管を接続してしまい、さらに、当初設計よりも細い口径の配管を使用したため、明らかに排水管としての口径が足りなくなり、トイレや消毒コーナーの洗面台などから水がボコボコと噴き出し、汚水が逆流するという事故が、少なくとも3回以上発生しました。そのため、事故発生日は、その日の予約を全てキャンセルして、新たな予約を設定し直して、清掃作業にも追われるなど、クリニックのスタッフは夜中まで作業をして、施主を含めて大変な苦労をされました。
そこで、本件では、修繕費用、営業損害、調査費用、弁護士費用などの通常損害の他に、特に慰謝料に注力して損害賠償請求することにしました。
訴訟の流れ
欠陥住宅裁判において、慰謝料請求は原則として認められません。それは、「①欠陥住宅は財産的損害である。②財産的損害によって精神的損害を被ったとしても、原則として、財産的損害の回復によって精神的損害も回復される。③財産的損害の回復によってもなお回復されない精神的損害があるという特段の事情が認められない限り、慰謝料請求は認められない。」という裁判所の理屈により、原則として認めらていれないのが現状です。
そこで、本件では、訴訟提起の段階で、施主の詳細な陳述書を作成し、下水の逆流事故が生じたときの多大な苦労を丁寧に説明し、写真や動画の撮影報告書を提出するなど、財産的損害の回復によってもなお回復されない精神的損害が分かりやすい主張立証を心がけました。
これに対し、施工業者は、修繕工事について争いましたが、特に慰謝料請求は徹底的に争う姿勢を見せました。
裁判の流れとしては、施主が業務多忙により早期解決を希望され、施工業者も早期解決を希望していたことから、裁判所から早い段階で和解が提案されました。その内容は、施主が請求している修繕費用、営業損害、調査費用などは認めて、施工業者が強く争っている慰謝料は認めないという内容でした。
特に慰謝料に注力していた事案であっただけに、精神的損害が全く考慮されないのは不満がありましたが、早期解決のため、裁判所の和解案に応じる形で事件終了となりました。
訴訟提起から和解成立まで約10か月かかりました。
コメント
欠陥住宅裁判において、慰謝料請求は原則認められません。被害者は実際に筆舌に尽くしがたい苦労をされている事案が多く、昨今は国民の権利意識も強くなってきていることから、裁判所の理論は実態を無視した時代錯誤なものに感じられ、被害者側の代理人としては大いに不満です。
被害者の精神的損害を軽視する日本の司法がいつか変わることを祈りつつ、これからも地道に救済活動を続けて参ります。
>>他の事例解説のページはこちら
建築コラム
■欠陥住宅裁判で負けないための被害者の心得
第1回 「立証責任」から考える建築訴訟の仕組み
効果的な主張とは
相談者から、交渉や訴訟の場で「業者の嘘を暴きたい、不誠実さを示したい、対応の悪さを明らかにしたい」と相談されることがあります。このような主張は果たして効果的でしょうか。
効果的な主張が何かを考える場合、まずは「立証責任」という裁判上のルールを理解することが重要です。
民事裁判では、必ずしも真実が明らかになるわけではありません。裁判所は、当事者間に争いのある事実を「証拠」によって判断しますが、証拠がない場合には判断に困ります。しかし、「証拠がないのでどちらとも判断できません」と言ってしまうと、当事者間の争いは永久に解決できなくなってしまいます。
そこで、裁判所の判断基準として、「立証責任」というルールが設けられました。これは、権利を主張する者が、その権利を裏付ける事実を証拠によって証明しなければならないという責任で、この証明に失敗すると、裁判所は権利を主張する者の請求を排斥できるのです。
したがって、民事裁判では、権利を主張する者が証拠の山を積み上げて立証活動を行い、この山が一定のラインを超えれば、立証責任を果たしたものとして、裁判所に請求が認められることになります。
これに対して、相手方は、「この証拠は信用できない」などと主張して、請求者が築き上げた証拠の山を崩す防御活動を行います。これを反証と言います。
このように、裁判所は、「当事者のどちらの主張が正しいか、正しい方を勝たせよう」と考えているのではなく、「請求者は立証責任を果たしているか、果たしていれば勝たせよう」と考えているのです。
さて、最初の問いに戻りましょう。「業者の嘘を暴く、不誠実さを示す、対応の悪さを明らかにする」という主張は効果的でしょうか。もうお分かりですね。
欠陥住宅裁判で業者の瑕疵担保責任・契約不適合責任を追及する場合、立証責任を負っているのは被害者です。被害者が立証しなければならないのは「欠陥(瑕疵・契約不適合)」です。「嘘つき、不誠実、対応が悪い」という業者の悪性格的な立証は、「欠陥(瑕疵・契約不適合)」の立証には直接役に立ちません。立証の山を崩すという業者の反証を弱める程度です。いくら悪性格立証に成功したところで、「欠陥(瑕疵・契約不適合)」の立証に失敗すれば負けてしまうのです。
冷静に考えれば当たり前のことかもしれませんが、感情的な対立の激しい欠陥住宅裁判では、実際に被害を被った側はどうしても業者の悪性格立証に注力しがちで、その結果、「欠陥(瑕疵・契約不適合)」の主張立証が十分に裁判所に伝わらずに負けてしまうことが少なくありません。
「立証責任」は裁判上のルールですが、効果的な主張を考えた場合、交渉でも同じことが言えます。被害者の「欠陥(瑕疵・契約不適合)」の主張立証がしっかりしていれば、交渉の場でも業者にとっては脅威です。これに対して、「嘘つき、不誠実、対応が悪い」と声高に主張したところで、業者にはほとんど効果がありません。むしろクレーマー扱いされるおそれがある分だけ逆効果と言えます。
被害者側が負けないためには、主張する中身を冷静に吟味する必要があるのです。
なぜ欠陥住宅裁判で被害者側が勝つのが難しいのか
「立証責任」のルールによれば、権利を主張する者が、その権利を裏付ける事実を証拠によって証明できれば勝ちます。そして、欠陥住宅裁判で被害者が立証しなければならないのは「欠陥(瑕疵・契約不適合)」であることはすでに学びました。では「証拠」は何でしょうか。
欠陥住宅の被害者にとって最大の証拠は、まさに「欠陥住宅そのもの」です。
しかし、他方で、欠陥住宅裁判では被害者側が勝つのが難しいという話を耳にします。なぜ最大の証拠を握っているはずの被害者側が勝てないのでしょうか。
その1つの答えを「立証責任」から考えてみましょう。立証とは、証拠によってある事実を証明することです。証明したと言えるには、当然のことながら、裁判所に理解してもらう必要があります。「よく分からない」と思われてしまうと「立証責任」を果たしていなものとして負けてしまいます。
この「立証責任」のルールは、離婚事件や契約トラブルなどの一般の民事事件では上手く機能しています。
ところが、医療過誤や建築紛争などの専門性の高い事件では、その事件を理解すること自体が難しいので、その分「立証責任」を果たす難度が高くなり、被害者側が勝つのが難しくなってしまうのです。ここに当事者間の不均衡が生じます。
この点、医療過誤事件では、「立証責任」を病院側に事実上転換することが裁判で認められており、当事者間の不均衡がある程度是正されています。
ところが、建築紛争の裁判では、何故か「立証責任」の事実上の転換という概念が認められておらず、当事者間の不均衡が残ったままです(裁判官が執筆した論考などでは、特定の欠陥現象があれば概括的な施工不良の事実が推認される旨の記述はありますが、実際の裁判で「立証責任」の事実上の転換が認められた例は寡聞にして知りません。)。
また、住宅の「欠陥(瑕疵・契約不適合)」は、建物の内部や地盤の中など、直接目に見えない箇所にあることが多く、さらには建築士や地盤品質判定士等の専門家の協力も必要となるなど、立証すること自体の苦労もあります。このような仕組みのため、欠陥住宅裁判で被害者側が立証責任を果たすのは容易ではなく、勝つことが難しいのです。
以上の説明は、欠陥住宅の被害者にとっては非常に辛い話だと思います。
しかし、それでも被害者側が裁判で負けないためのノウハウというのはあります。次回からもう少し具体的にお話ししていきたいと思います。
>>第2回のコラムのページはこちら
建築コラム
■建築トラブルに役立つ基礎知識
これまでに法律相談で受けたいろいろな質問の中から、代表的な質問について解説していきます。
■建築トラブルの相談のポイント
相談時に何を持って行けばいいの?
相談時に用意していただきたいものは、まず、どのような内容の工事を合意したのかが分かる書類です。具体的には、契約書、契約約款、設計図書、見積書などです。設計図書には、契約書添付の設計図書、確認申請書添付の設計図書、竣工時の設計図書などがあります。次に、どのような不具合があるのかが分かる資料です。具体的には、不具合を撮影した写真、動画、不具合について専門家が調査した調査報告書などです。その他参考資料としては、不具合に関して、建築会社とのやり取りが分かるメールやFAXなどです。
経緯が複雑な場合は、時系列などを予めまとめて頂けると、相談をスムーズに進行できます。
対面相談とWeb相談、どっちがいいの?
建築トラブルの相談では、設計図書などの書類を確認することが多いので、対面による相談の方が分かりやすいと言われています。ですが、紙媒体の資料は、予めPDFにして頂けると、Web相談でも閲覧共有できるので、対面相談とほぼ変わらない形で進行することが可能です。ですから、それほど気にすることなく、時間の都合や好みなどで決めてよいかと思います。
最近では、建築裁判もWeb裁判で行われるようになり、とくに不便を感じることもありません。
>>他のコラムのページはこちら
建築コラム
■基本のキホン
建築トラブルに関する用語をもとに、基本中のキホンを解説します。